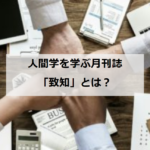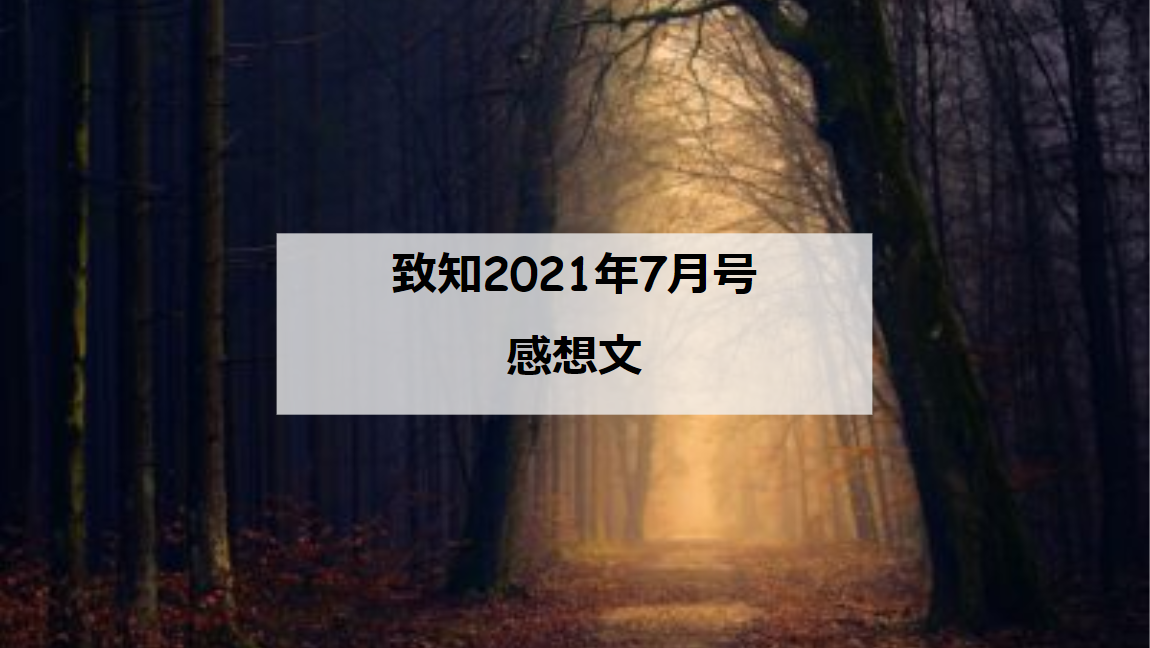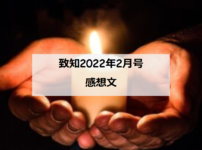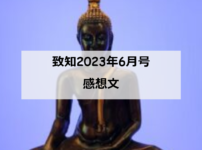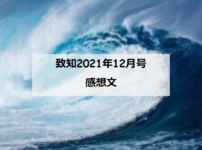2021年7月号のテーマは「一灯破闇」(いっとうはあん)です。
感想を書いていきます。
-
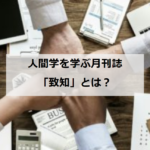
-
参考【致知】人間学を学ぶ月刊誌「致知」について
当ブログでは、致知出版社の月刊誌「致知」という雑誌を読んだ感想を月に一度書いています。 参考 今さらになりますが、この「致知」がどういった雑誌なのか?世の中でどう活用されているのか?なぜ僕が読んでいる ...
続きを見る
スポンサーリンク
一灯破闇とは?
一灯破闇とは、漢字のとおり「一灯、闇を破る」ことで、陶芸家・河井寛次郎さんが創作した言葉だそうです。

特集には、
- 将棋の第15代名人・大山康晴さんがこの言葉を心に刻んでおり、ピンチになった時にこの言葉を思い出す。
- Aさんは「修身教授録」を読んで、一灯破闇の機会を得た。
リンク
- 月刊誌「致知」が、誰かの人生の闇を破る一灯となり得たことは感無量である。
といったことが書かれています。
スポンサーリンク
感想
特集の最後に書かれているように、誰かの人生の闇を破る一灯となることは、自分自身が生きていくうえでのエネルギーの根源になるのではないかと思います。
仕事目線で考えると、報酬はお客様からいただくものなので、誰かの役に立つことをしてあげなければ成功することはありません。
またプライベートにおいても、家族など身近な人のことを真剣に考えてサポートすることで、その人の人生の闇を破ることができます。
いずれにしても、自分から行動したり発信しなければ一灯になることはできません。
自分がやりがいを持ってできることをコツコツやっていれば、いつかどこかで誰かの役に立つことがあるかもしれません。
何も分からないまま始めたブログも1年でだいぶアクセス数が増えました。
少しでも何かしらの結果として表れると、もっとやってやろうというエネルギーにすることができます。
受け身ばかりにならず、積極的に行動していきましょう。
関連記事
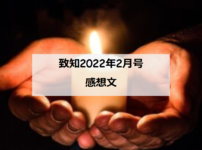
致知
2022/1/6
【致知】2022年2月号「百万の典経 日下の燈」を読んだ感想
致知2022年2月号のテーマは「百万の典経 日下の燈」です。 スポンサーリンク 百万の典経 日下の燈とは 「百万の典経 日下の燈」 百万本のお経を読んでも、行動しなければ意味がない。 明治時代の禅僧である今北洪川という人の言葉で、この人物について調べてみると、以前致知にも取り上げられたことのある鈴木大拙の師匠のようです。 鈴木大拙は相当行動力のある方だったので、これはきっと師匠譲りのものでしょう。 スポンサーリンク 印象に残ったところ 印象に残ったところは、「1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教 ...
ReadMore
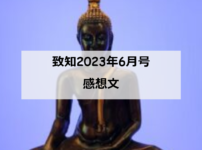
致知
2023/5/9
【致知】2023年6月号「わが人生の詩」を読んだ感想
致知2023年6月号の特集は「わが人生の詩(うた)」です。 それでは、感想を書きます。 スポンサーリンク 人生で欠かしてはならない大切なもの 人生の師 人生の教え 人生を共に語り合える友 最近仏教に関する本を色々読んでいるのですが、このような教えがあることを初めて知りました。 なんか釈迦らしくない気もしますがそれは置いておいて、これらが生きていくうえで欠かしてはならないものかどうかは分かりませんが、人生をより豊かにするものであるようには思いますね。 スポンサーリンク 感想 人生をより豊かなものにするために ...
ReadMore

致知
2025/10/3
【致知】2025年11月号「名を成すは毎に窮苦の日にあり」を読んだ感想
致知2025年11月号の特集は「名を成すは毎に窮苦の日にあり」というテーマです。それでは感想を書いていきます。 名を成すは毎に窮苦の日にあり 誰しもが、成功への過程で窮苦が訪れるとのことです。 そもそも人生というのは、その窮苦の時が一番楽しく充実している時ではないでしょうか。 「人生ゲーム」というボードゲームがありますが、もしもスタートの次のマスがゴールになっていたら楽しいでしょうか。 ジェットコースターのように浮き沈みがあるから人生は充実するものだし、自分自身が成長する機会だと思っています。 リンク ス ...
ReadMore

致知
2025/9/3
【致知】2025年10月号「出逢いが運命を変える」を読んだ感想
2025年10月号の特集は「出逢いが運命を変える」というテーマです。それでは感想を書きます。 スポンサーリンク 人との出逢いとは限らない 運命を変えるような出逢いは、人との出逢いとは限らないような気がします。本、映画、音楽、SNSなど、心を動かされるような出逢いというのは、身近なところに存在しているものです。 特集には、自身のレベルを高めていけないと書かれていますが、具体的に何のレベルのことなのか、何をすればそのレベルを高められるのかよく分かりません。 僕は、自分自身の理想や本心を明確にしたうえで、それに ...
ReadMore
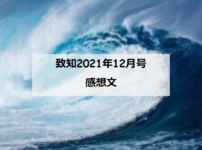
致知
2021/11/7
【致知】2021年12月号「死中活あり」を読んだ感想
致知2021年12月号のテーマは「死中活あり」です。 この言葉は安岡正篤氏の「六中観」で挙げられている、6つの言葉の中の1つだそうです。 その意味や感じたことについて書いていきます。 スポンサーリンク 「死中活あり」とは? 六中観の中の1つ、死中活ありは以下のような意味を持っています。 もう駄目だという状況の中にも必ず活路はある。 死中においても必ず活路を見出せるという、かなり前向きな言葉です。 この言葉以外の5つの言葉については、死中に活路を見出すために必要な要因としての位置付けであり、生きていくうえで ...
ReadMore
関連