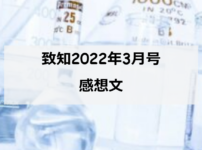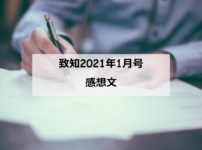致知2021年9月号のテーマは「言葉は力」です。
シンプルでありながら力強いテーマです。
それでは、読んだ感想です。
スポンサーリンク
目次
Toggle言葉は命の元となる
美しい言葉や心を鼓舞する言葉は、人間の命の元となるとのことです。
また逆に、汚水が花を枯らすように、人を貶め損なうような言葉は、人間の心を腐らせ滅ぼす、とも書かれています。
大人になって、人を傷付けるような言葉はできるだけ口に出さないように意識するようになりましたが、子供が産まれてからはついつい子供に対してきつい言葉をかけてしまうことがあります。
子供がたまに僕と同じような汚い言葉を使うのはその影響があるのでしょう。
気を付けます。
スポンサーリンク
人間的器量が大事
柴山全慶老子の「越後獅子禅話」に書かれたエピソードが紹介されています。
そのエピソードを受けて、「言葉を受け取る側の力量も問われる」「受け入れるだけの人間的器量を養っておきたい」と書かれていますが、それだけでなく言葉を発する側の力量も問われます。
いくら美しい言葉を投げかけても、それを発する人の人間性が優れていなければ、受け手の心を揺さぶることはできません。
子供にとって自慢の父親となり、子供に強い生命力を与えられるようになりたいです。
【致知】2022年3月号「渋沢栄一に学ぶ人間学」を読んだ感想
致知2022年3月号のテーマは「渋沢栄一に学ぶ人間学」です。 新一万円札に描かれることになっている渋沢栄一の功績、そしてその人間性からはたくさんの学ぶことがあるという内容です。 感想を書きます。 スポンサーリンク 3つの魔 渋沢栄一は3つの魔を持っていたとのことです。 吸収魔:よく勉強し吸収をやまない人 建白魔:よく立案、企画、建白する人 結合魔:人と人とを結びつけてやまない人 魔というのは、それだけ打ち込んだということだそうです。 スポンサーリンク 感想 3つの魔のうちの上2つは、いかにも仕事ができる人 ...
致知2021年5月号のテーマは「命いっぱいに生きる」です。 紹介されている言葉と感想を書きます。 スポンサーリンク 先達の4つの言葉 1.小林秀雄氏の言葉 力は乏しくても精一杯生きているものは真実である。 2.森信三氏の言葉 人間の偉さは才能の多少よりも、 己に授かった天分を生涯かけて出し尽くすか否かにあるといってよい。 スポンサーリンク 3.平澤興氏の言葉 偉い人というのは生活の中に燃える情熱を持って、 自分の持っておる140億の大脳皮質の神経細胞を生かした人だ。 4.坂村真 ...
【致知】2021年10月号「天に星 地に花 人に愛」を読んだ感想
2021年10月号のテーマは「天に星 地に花 人に愛」となっています。 それでは感想を書きます。 スポンサーリンク 当たり前のことだけど、、、 書かれている本文そのままですが、 天に星が輝き、 地に花が咲き、 人に愛がある このことによって、人間の命は保ち続けられているとのことです。 僕は、たまに夜散歩をするので、星はよく見ます。 庭には花が咲いています。 そして愛すべき子供もいます。 当たり前のように存在して特に何も意識していないので、このような当たり前があって自分や子供の命があることを忘れてしまいます ...
2021年1月号の致知のテーマは「運命をひらく」です。 「そもそも致知ってなんだ?」という方は下の記事を参考にしてください。 それでは、特集を読んで感じたことですが、 MrSaka二宮尊徳の言葉が至高! ということです。 スポンサーリンク その言葉というのは、特集の最後に紹介されていた言葉です。 我が道は至誠と実行のみ。 故に才智、弁舌を尊ばず。 至誠と実行を尊ぶなり。 およそ世の中の人は智あるも学あるも、 至誠と実行とにあらざれば事は成らぬものと知るべし。 日常ではあまり聞かない単語の意味を1つ1つ調べ ...
2022年7月号のテーマは「これでいいのか」です。 特集ページの最後にあるように、日本が置かれている現状について「このままではいけない」ということが書かれています。 このようにテーマ名が問題提起の形になっているのは、これまで見たことがないような気がします。 スポンサーリンク 日本の現状 日本は今、内憂外患の時にあるとのことです。 内憂外患とは、内にも外にも問題を抱えているやっかいな状態を意味します。 特に問題とされているのは内憂の方で、人心の病み・衰弱を復活させることが課題として挙げられています。 &nb ...
【致知】2022年3月号「渋沢栄一に学ぶ人間学」を読んだ感想
致知2022年3月号のテーマは「渋沢栄一に学ぶ人間学」です。 新一万円札に描かれることになっている渋沢栄一の功績、そしてその人間性からはたくさんの学ぶことがあるという内容です。 感想を書きます。 スポンサーリンク 3つの魔 渋沢栄一は3つの魔を持っていたとのことです。 吸収魔:よく勉強し吸収をやまない人 建白魔:よく立案、企画、建白する人 結合魔:人と人とを結びつけてやまない人 魔というのは、それだけ打ち込んだということだそうです。 スポンサーリンク 感想 3つの魔のうちの上2つは、いかにも仕事ができる人 ...
致知2021年5月号のテーマは「命いっぱいに生きる」です。 紹介されている言葉と感想を書きます。 スポンサーリンク 先達の4つの言葉 1.小林秀雄氏の言葉 力は乏しくても精一杯生きているものは真実である。 2.森信三氏の言葉 人間の偉さは才能の多少よりも、 己に授かった天分を生涯かけて出し尽くすか否かにあるといってよい。 スポンサーリンク 3.平澤興氏の言葉 偉い人というのは生活の中に燃える情熱を持って、 自分の持っておる140億の大脳皮質の神経細胞を生かした人だ。 4.坂村真 ...
【致知】2021年10月号「天に星 地に花 人に愛」を読んだ感想
2021年10月号のテーマは「天に星 地に花 人に愛」となっています。 それでは感想を書きます。 スポンサーリンク 当たり前のことだけど、、、 書かれている本文そのままですが、 天に星が輝き、 地に花が咲き、 人に愛がある このことによって、人間の命は保ち続けられているとのことです。 僕は、たまに夜散歩をするので、星はよく見ます。 庭には花が咲いています。 そして愛すべき子供もいます。 当たり前のように存在して特に何も意識していないので、このような当たり前があって自分や子供の命があることを忘れてしまいます ...
2021年1月号の致知のテーマは「運命をひらく」です。 「そもそも致知ってなんだ?」という方は下の記事を参考にしてください。 それでは、特集を読んで感じたことですが、 MrSaka二宮尊徳の言葉が至高! ということです。 スポンサーリンク その言葉というのは、特集の最後に紹介されていた言葉です。 我が道は至誠と実行のみ。 故に才智、弁舌を尊ばず。 至誠と実行を尊ぶなり。 およそ世の中の人は智あるも学あるも、 至誠と実行とにあらざれば事は成らぬものと知るべし。 日常ではあまり聞かない単語の意味を1つ1つ調べ ...
2022年7月号のテーマは「これでいいのか」です。 特集ページの最後にあるように、日本が置かれている現状について「このままではいけない」ということが書かれています。 このようにテーマ名が問題提起の形になっているのは、これまで見たことがないような気がします。 スポンサーリンク 日本の現状 日本は今、内憂外患の時にあるとのことです。 内憂外患とは、内にも外にも問題を抱えているやっかいな状態を意味します。 特に問題とされているのは内憂の方で、人心の病み・衰弱を復活させることが課題として挙げられています。 &nb ...
【致知】2022年3月号「渋沢栄一に学ぶ人間学」を読んだ感想
致知2022年3月号のテーマは「渋沢栄一に学ぶ人間学」です。 新一万円札に描かれることになっている渋沢栄一の功績、そしてその人間性からはたくさんの学ぶことがあるという内容です。 感想を書きます。 スポンサーリンク 3つの魔 渋沢栄一は3つの魔を持っていたとのことです。 吸収魔:よく勉強し吸収をやまない人 建白魔:よく立案、企画、建白する人 結合魔:人と人とを結びつけてやまない人 魔というのは、それだけ打ち込んだということだそうです。 スポンサーリンク 感想 3つの魔のうちの上2つは、いかにも仕事ができる人 ...
致知2021年5月号のテーマは「命いっぱいに生きる」です。 紹介されている言葉と感想を書きます。 スポンサーリンク 先達の4つの言葉 1.小林秀雄氏の言葉 力は乏しくても精一杯生きているものは真実である。 2.森信三氏の言葉 人間の偉さは才能の多少よりも、 己に授かった天分を生涯かけて出し尽くすか否かにあるといってよい。 スポンサーリンク 3.平澤興氏の言葉 偉い人というのは生活の中に燃える情熱を持って、 自分の持っておる140億の大脳皮質の神経細胞を生かした人だ。 4.坂村真 ...
【致知】2021年10月号「天に星 地に花 人に愛」を読んだ感想
2021年10月号のテーマは「天に星 地に花 人に愛」となっています。 それでは感想を書きます。 スポンサーリンク 当たり前のことだけど、、、 書かれている本文そのままですが、 天に星が輝き、 地に花が咲き、 人に愛がある このことによって、人間の命は保ち続けられているとのことです。 僕は、たまに夜散歩をするので、星はよく見ます。 庭には花が咲いています。 そして愛すべき子供もいます。 当たり前のように存在して特に何も意識していないので、このような当たり前があって自分や子供の命があることを忘れてしまいます ...