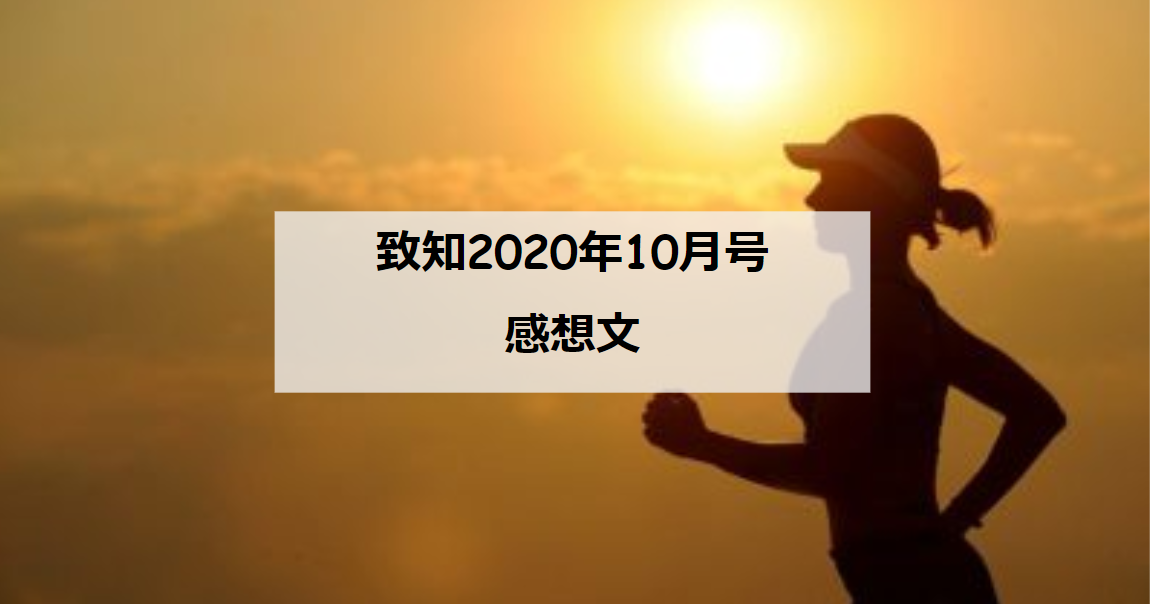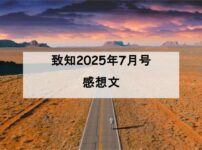僕は、テーマになっている「人生は常にこれから」という言葉はとても好きです。
特集では、そのテーマにちなんだ何名かの偉人さんたちの名言が取り上げられています。
僕が連想して思い出した好きな言葉と合わせて紹介します。
スポンサーリンク
小篠綾子
私の人生はこれからや
小篠綾子(こしの あやこ)さんというのは、世界的デザイナー・コシノジュンコさんのお母さんです。
テーマの言葉ほぼそのままですが、ストレートな言葉は心に響きますね。
小篠綾子さんですが、なんと90歳を過ぎてから10数人の恋人を持つほどのモテモテ女だったようです。
この言葉が生まれた背景が意外な状況でしたが、恋愛以外にも通用する前向きな言葉です。
世阿弥
住する所なきをまず花と知るべし
世阿弥(ぜあみ)とは、あの観阿弥・世阿弥の世阿弥さんです。
昔の言葉なので少し分かりにくいですが、訳すと以下のようになるようです。
現代語訳
とどまらずに学び続けることこそ花だ
⇒常に学び続けることで幸せになれる
「花だ」の訳し方が色々あるかもしれませんが、基本的に花という言葉には「良いこと、プラスなこと」のようなイメージがあるので、「学び続けるのは大事なことだ」と伝えたいのであろうと思います。
僕は歳をとるにつれてこの感覚が分かってきたような気がします。
若い頃は、「1日中ゴロゴロしたいなぁ」とか「仕事めんどくさいなぁ」とかいう気持ちが強かったのですが、最近はゴロゴロしている時間がもったいないと思うようになりました。
1日中ゴロゴロして暮らしたり、仕事をやめて暮らしたいのであれば、早いうちから努力して遊んで暮らせるほど多くの資産を築くしかないです。
体力的にまだまだ元気なうちは、いろいろなこと(本業のお仕事以外にも!!)に挑戦しなければ、いつまで経っても花は見つからないでしょうね。
本の表紙に書いているとおり、やるかやらないかはあなた次第です。
今の時代に何もしないというのはもったいないです。
是非一度読んで、参考にしてみてください。
-
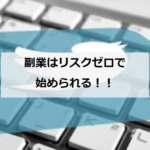
-
参考【資産運用】副業を始めたい方必見!リスクを抑えて副業を始める方法!
資産運用においては、「お金に関する5つの力」が重要だと言われています。(両学長より) メモ 貯める力・・・支出を減らす 稼ぐ力・・・収入を増やす 増やす力・・・資産を増やす 守る力・・・資産を減らさな ...
続きを見る
平澤興
生きるとは情熱を持って燃えることだ。
燃える心を忘れているような生き方は気の毒な生き方ではないでしょうか。
全くそのとおりです。
会話しても何に情熱を燃やしているのか分からない人には何の魅力もありません。
他人がどうこう言うことではありませんが、

と感じます。
くだらないことでもいいから何かしら目標を持って生きていくべきだと思っています。
スポンサーリンク
連想して思い出した言葉①
今日という1日は残りの人生の最初の1日
僕が崇拝しているM.Childrenの桜井和寿さんが一番好きな言葉として挙げていました。
僕が知っている限りでは、同じようなフレーズが、
RADWIMPSの曲「叫べ」(アルバム「アルトコロニーの定理」収録の名曲)
伊坂幸太郎の小説「終末のフール」(名作)
映画「アメリカン・ビューティー」(名作)
にも出てきます。
朝起きてこの言葉を思い出すとやる気が出ます。
連想して思い出した言葉②
今日が一番若い日
YouTubeやTwitterで注目を浴び、「お金の大学」という本の著者である両学長が度々口にする言葉です。
副業を始めたり、資産運用を開始するのに早い遅いはありません。
もちろん早ければ早いほど良いに決まっているのですが、自分のこれからの人生で一番若いのは今日ですから、とにかく何か始めようかと思った時には、明日からではなく、まずは今日、今すぐ、少しでもいいから手を付けるようにするべきです。
スポンサーリンク
まとめ
「人生は常にこれから」と思うことで、年齢なんか関係なくいつでもチャレンジできます!
行動力を発揮し、生きている限り走り続けましょう!
こちらもCHECK
-
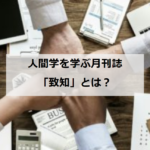
-
【致知】人間学を学ぶ月刊誌「致知」について
当ブログでは、致知出版社の月刊誌「致知」という雑誌を読んだ感想を月に一度書いています。 参考 今さらになりますが、この「致知」がどういった雑誌なのか?世の中でどう活用されているのか?なぜ僕が読んでいる ...
続きを見る
関連記事